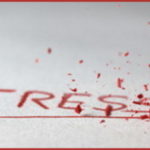不整脈は高齢になってからの病気と安易に考える、あるいは不整脈と診断されて、自分は重症だ、余命が短いなどと恐怖感ばかり抱いている方もいるのではないでしょうか。
不整脈とは病気なのでしょうか、どんな原因があるのでしょうか、不整脈についてしっかりと知識を持ち、緊急時の対処や、診断後の生活に役立てましょう。

不整脈、本当の恐怖は?不整脈のメカニズムから原因対策まで!
不整脈とは電気の流れが問題!
■不整脈とは
普段から心臓のドクンドクンというリズムは感じられます。不整脈とはこうした一定のリズムや速さが狂ってしまうことを言います。しかしこのリズムとはいったいどこから発せられるのでしょうか。
心臓は全身を周り老廃物を含んだ静脈と、酸素や栄養をたっぷり含んでいる動脈の入れ替わる基点であり、これらの血液を巡回させるポンプの働きを担う場所です。
心臓は収縮や拡張という拍動を繰り返すことで、血液を押し出しています。こうして心臓が動くのは、私たちがコントロールできるものではなく、心臓の筋肉が特別な働きをしているからなのです。
心臓の中には電気を発生させる細胞があり、自分で動きを起こします。この部分を洞結節と呼び、1分間に60~80回程度の興奮を作り上げ、心臓の4つの部屋(左右の心房、左右の心室)を通過し心臓を収縮させます。
洞結節のルートは以下となります。
「心房を通過しながら筋肉を収縮→房室結節→ヒス束→左脚と右脚→プルキンエ線維→心室の収縮」
つまり「不整脈」とは、この電気系統が何らかの故障を起こすことで生じる症状のことなのです。
■不整脈はなぜ起こるのか
不整脈が起きる原因は、心臓の電気系統の不調です。具体的には電気を発する源はイオンチャンネルといわれるタンパク質で、そのたんぱく質の誤作動から刺激伝導系の異常が起きることになります。この異常はっする原因としていくつかあげられます。
先天的に刺激伝導系の異常がある場合と、病気に起因するもの、加齢による電気系統の機能の低下、体質や心因性のものなどです。
不整脈が起きると心筋梗塞や狭心症など血管の病気に発展すると考えがちですが、実は反対であり、病気があってこそ、二次的に刺激伝導系の異常を来たすことになります。狭心症や心筋梗塞のほかにも、心不全、心臓弁膜症、肺疾患、甲状腺疾患などが原因となることがあります。
体質や心因性からの影響という点では、ストレスや睡眠不足などは自律神経に作用し、バランスを崩すことになります。自律神経である交感神経や副交感神経は直接心臓機能に関与するものですので、二次的に刺激伝導系に悪影響を与え不整脈につながるというわけです。
不整脈の種類は3つのリズム不整が基本
脈のリズムが1つ2つと抜けるような不規則なリズムになったり、脈拍数が正常値より多くなる少なくなるということが不整脈といわれます。
心臓の1分間の拍動は、およそ50から100回が正常な数値ですので、これを基本に考えます。
■頻脈(ひんみゃく)
運動や興奮した状態ではなく平静時の脈拍が1分間に100回以上の場合を頻脈といいます。
電気の信号が異常に早くなるか、通常の電気伝導回路とは異なったルートができてしまったため、空回りが起きている状態が考えられます。
頻脈の中にも心臓のどの部分に異常が起きているかによって病名が分かれます。
心房や房室結節の異常で起こる頻脈を「上室性頻拍」、「WPW症候群」、「心房粗動」、「心房細動」。
心臓の心室に起きている頻拍では「心室頻拍」、「心室細動」などがあげられます。
中でも心室頻拍や心室細動は、血圧低下や心停止などにつながる危険な頻拍として扱われています。
■徐脈(じょみゃく)
平常時の脈拍が1分間に50回以下の場合を徐脈といいます。
電気の信号が送れなくなったり、途中で止ってしまったりすることで徐脈となります。
高齢者や心筋が酸欠状態になる虚血性心疾患を持った方に多く見られます。
徐脈にも種類があり、「洞性徐脈」、「洞停止」、「洞房ブロック」、「房室ブロック」などがあります。
洞性徐脈は治療の対象にならない程度で、害はないとされていますが、他の3種は突然死につながる可能性がある徐脈です。
■期外収縮(きがいしゅうしゅく)
脈のリズムが「トン、トン、-、トン・・・」や、「トン、トン、トトン・・・」などと不規則になったり抜けたりする場合を期外収縮といいます。
通常の電気信号回路とは異なった場所から発生し、横入りしてしまうことで生じます。
期外収縮も種類分けされており、「心房性期外収縮」や「心室性期外収縮」などがあります。
どちらも程度によって重症度の評価は変わってきます。
怖い不整脈にはこんな自覚症状がある
不整脈は何らかの病気を持っているから起こる、自分には持病がないから大丈夫と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実際には中高年になると持病に関係なく不整脈の1~2個は心電図中に現れるものです。
心臓の働きは1日に約10万回以上といわれます。心臓をはじめ、体全体の機能が衰えていくのも当然であり、ストレスや疲労を感じやすくなり、眠りも浅くなったりします。
こういった原因からも不整脈が出現しても特異ではないのです。
しかし、不整脈の中には緊急を要するものもあります。
■意識を失う
不整脈の自覚症状もなく、特に急激に動く、体制を変えるなどの変化がない状況なのに、急に意識が遠くなる、または失神してしまう。
これは電気系統の異常によって心臓の動きが狂ってしまい、けいれんのように頻脈になっていたり、心臓が適応できないために、一時的に停止している可能性があります。
自然に覚醒し、もとの状態に戻ったとしても早急な病院受診が必要となります。
■動いたときの息切れ
脈泊数が不足する徐脈状態(1分間40回以下)となっていることが考えられます。
脈が遅くなり、動いてるときには息切れや気が遠くなるなどの症状があると心不全の可能性があります。
電気系統の故障によって心臓の動きが衰えてしまい、全身に送る血液量が減ってしまうことになります。
病院での詳しい検査が必要です。
■突然の動悸
自分の心臓の動きが振動するように大きく感じられ、時には脈拍が確認できなくなったり、息苦しさや異常な発汗なども見られます。
この時点では、実際の脈拍は1分間に120回以上から200回を超える数値になることがあります。
また不規則なリズムが続いたり、不規則と規則的が入り混じったりと脈拍の乱打が起こっていることがあります。
心筋梗塞の持病を持っている方で、かつ心室の不整脈となると、心室細動という最も危険な不整脈に変化する場合がありますので十分な注意が必要です。
■バラバラの規則で速い脈
原因は加齢であることが一番にあげられる心房細動です。
心房の数百回という興奮ですが、次の心室に作用する興奮を、中間の房室結節がコントロールし、寝室に正常な電気を送ると、動悸や息苦しさなどの自覚症状が出ないことが多いのが特徴です。
心房細動自体が命にはかかわりませんが、心臓病を持っている方であれば心不全に移行する可能性が出てきます。
また血管内に血の塊を作りやすくしてしまうため、それが脳塞栓などを起こす危険性があります。
診察を受け、継続的な内服治療が必要となります。
なぜストレスから不整脈になるのか
ストレスという言葉も周知され、目に見えないけれども体にとって悪いエキスのようなものと漠然とした知識も持っている方が多いことでしょう。
このストレスは心臓にとっても害になるといわれますが、どんな経路で不整脈の原因となってしまうのでしょうか。
■ストレスって、どんなもの?
ストレスという言葉も物理学の用語を用いたもので、心身が歪んでしまうという意味を含めた言葉です。
心身を乱す要因となる刺激物を「ストレッサー」といい、それを受ける方の耐性能力や周囲の援助などで差し引きされて残った分のダメージが「ストレス」となります。しかし実際には、攻撃要素も含めてストレスと一般的には呼ばれています。
ストレッサーとなるものは精神的な苦痛ばかりではありません。感情の変動も、気温の変化も、肉体的な疲労や病気、嫌な臭い、引っ越しなどの環境の変化などと多くのものがあげられます。
■ストレスを受けると自律神経が乱れる
ストレスを受けると、体は自身を守ろうと数々の動きをし始めます。その中のひとつが体の機能をコントロールする自律神経です。
ストレスとなる刺激は脳の視床下部に伝えられ、次にホルモンを作用するルートと自律神経のルートに分かれて伝えられます。
自律神経は交感神経と副交感神経に分かれていますが、交感神経のスイッチをONにし、アドレナリンやノルアドレナリンの分泌を促進していきます。緊張すると汗が出たり、手足が冷たくなったり、心臓がドキドキすると言った症状は、交感神経が優勢となっている証拠ということになります。
■ストレスはこうして心臓に関わっていく
自律神経は交感神経と副交感神経が均衡を図ってこそ、正常な働きをします。
交感神経は体の一大事にあらゆるものを興奮させて闘おうとし、副交感神経は逆にリラックスさせながらエネルギー補給するといった役割になります。
交感神経が活発に前にでてしまうと、血管を収縮させたり、脈拍数を増やし心臓をどんどん動かしていきます。こういった状況が繰り返されると心臓が疲れ果てる、または心臓の酸素が不足してしまい心筋梗塞になるなど危険な状態になることがあります。
心筋梗塞は心筋が壊死する病気ですので、心筋をベースに働く電気系統は当然のように狂い、不整脈となります。
不整脈と糖尿病の間接的な関係
■糖尿病患者さんが不整脈を起こしやすい理由は?
糖尿病はインスリンの働きが悪くなることで血管内にぶどう糖が残ってしまいます。こういった状態が継続することでインスリンが必要な箇所での抵抗性が高まってきます。
更には処理しきれないぶどう糖が血管を傷め、神経障害をも引き起こすといった病気です。
不整脈を起こしやすい病気はいくつかあげられますが、糖尿病もその中のひとつで、糖尿病患者さんでは、不整脈を合併する率が40%も引き上げられるといわれます。
未だきっちりと立証されてはいませんが、自律神経障害や、代謝障害から心臓の筋肉が線維化したり、機能の低下を来たすという理由や、酸化ストレス、炎症を起こしやすい体質になるといったことから不整脈につながるという説があります。
■糖尿病患者さんが注意しなければならない点は?
糖尿病患者さんが不整脈で気をつけなければならないのが「心房細動」です。
心房細動は持続することで血栓が生じやすくなり、心筋梗塞や脳梗塞につながりやすいといった恐ろしい点があります。
また不整脈が起こっているときは、歩いたり動いたりしているときに胸の圧迫感を感じることが多いのですが、糖尿病特有の苦痛や痛みの自覚が鈍くなるということで、無症候性になるケースがあります。
糖尿病が悪化する前に、少しでも心臓や脈拍の異変を感じた際にはすぐに医療機関で検査することが必要です。
不整脈の検査方法5つ
■12誘導心電図検査
健康診断でも行われる一般的な心電図です。心臓の筋肉が収縮することで発生する電流をキャッチし、波形で表し、幅や高さ数などで異常を読み取っていくものです。安静を確保して検査するものなので、運動による筋肉の電流を制することができますが、検査中のその一時だけの異常しかわかりません。
■ホルター心電図
通常の心電図では短時間の記録という点に対して、ホルター心電図は24時間の記録となります。
電極を体に貼り付けたまま通常の日常生活を送ってもらい、データーは自動的に録画されるため詳しい心臓の状態が診断できます。
■運動負荷心電図
電極を貼り付けたまま運動をしてもらい、心臓に負荷をかけ、運動時の不整脈の有無や心臓の変化を検査することになります。
運動方法にはエルゴメーターやトレッドミルなどが用いられますが、エルゴメーターは自転車をこぐ、トレッドミルはベルトコンベアのような上を歩くといった方法です。
■心臓超音波検査
心エコー検査とも言われる検査で、超音波を当てることによって反射を映像化して見るものです。注射や苦痛を伴う検査ではありません。
心臓の弁や部屋、筋肉の状態、動き方、収縮力などが確認できるため、不整脈の原因となる疾患などがある程度特定できます。
■心臓電気生理検査
EPS検査とも言います。足の付け根にある静脈に電極カテーテルを挿入し、心臓まで進めていきます。外からの心電図ではわかり得ない、電気系統の異常の有無、どこから発生するか、どういった発生の仕方なのかなど詳しい情報を得ることができます。
検査自体は数時間ですが、局所麻酔などを使用しますので、2~3日の入院を必要とします。
不整脈と診断されたら、気をつけたい食事のポイントはこれ
病気は普段の生活が大きな影響を与え、中でも食事は重要な役割を担います。
不整脈で気をつけなければならない食事のポイントを心得ておきましょう。
■塩分
塩分を多く摂ってしまうと、血管内のナトリウムを薄めようと水分抱え込むため、血管に大きな負担がかかってきます。繰り返すことで動脈硬化や心臓疾患につながり、不整脈を起こすことになるので、1日7gから10gを目安に調節していきましょう。
調味料は煮込んだりかけて食べるよりは、少しの量をつけて食べたほうが、摂り過ぎを抑えられ、また塩分の代わりに香辛料などの代用も効果的です。
■脂肪分
脂肪分の摂り過ぎは、血管内にコレステロールの塊を作り、動脈硬化や心臓疾患に発展し、不整脈の要因となります。
肉でも脂身の部分や魚の内臓は飽和脂肪にあたり、コレステロールを高めますので、代わりにコレステロールを抑える役割の不飽和脂肪酸を含む植物性油や魚類を摂取するようにしましょう。
特に制限がなければ、飽和脂肪酸:不飽和脂肪酸=1:2の割合が理想的です。
■摂取カロリー
塩分も多くなく、肉でもないからといって炭水化物や糖質を多く摂っては、カロリーオーバーになります。
肥満になると体のあらゆる部分に対してマイナス効果が高くなります。心臓にも負担がかかり不整脈の原因となりますので、標準体重を意識しながら、食事と運動の上手な調節をしていきましょう。
■食物繊維
食物繊維は胃腸の余分なものを絡めながら排泄へと導く素材で、便通もよくなり、肝臓にため込まれたコレステロールを消費する性質がありますので、肥満予防にもなります。
食物繊維は緑黄色野菜、海藻類、きのこ類、雑穀に多く含まれています、積極的に摂ることがいいでしょう。
ただし、野菜にはカリウムを多く含む物がたくさんあります。疾患がなければ問題ありませんが、腎臓疾患を持っている方はカリウムを体内に蓄えてしまいますので、摂取量を制限されます。腎疾患がある場合は医師の指示に従いましょう。
不整脈と診断された時の対処法
不整脈は心臓の伝導回路のどの部分の異常かによって種類分けされます。
不整脈と診断された場合には、生活上どんな対処が必要なのか把握しておくことも大切です。
■期外性収縮と診断されたら
30代以降に多く見られる不整脈です。もともと決まったルートで流れてくる電気とは別の場所から発せられものですが脈がはっきりしないため、1拍抜けたような脈拍となります。
期外性収縮も上室性、心室性、心房性と3つに分かれ、心筋梗塞や狭心症、弁膜症などの病気が原因で生じるものがありますので、こういった病気が背景にあるかどうかの精査をすることが必要です。
しかし期外性収縮の多くは病気ではなく精神的、肉体的ストレスや疲労などが起因して生じるものが多いのが特徴です。ストレスや疲労をためないという生活習慣を心がけ、また背部や肩のコリからつながることもあるので、定期的な運動も行っていきましょう。
■洞不全症候群と診断されたら
電気を発する場所において、電気が作られなくなることで起こる不整脈です。
頻脈の場合も徐脈の場合もあります。頻脈の場合は発作がおさまった時に心臓が停止しやすくなる、徐脈の場合ではそのまま心不全につながるといった現象が起きやすくなります。
症状が現れた時には失神してしまうケースがあるので運転や転倒で事故を起こさないように気を付ける必要があります。
また高血圧や心疾患の薬によっても洞不全が起きることがあるため、内服中の方はそういったことを意識しながら行動することが良いでしょう。
■房室ブロックと診断されたら
房室ブロックでは伝わる電気が時々途切れてしまうものと、完全に止まってしまうもの二つがあります。ブロックされたからといって心臓が必ずストップするというものではなく、心室から自家発電して電気を流すという独自の機能で心臓の動きは維持されます。
しかしブロックを起こす原因が心筋梗塞や心筋症である場合は、徐脈からそのまま心停止となることがありますので、要注意となります。重症度によってはペースメーカー手術を受けることが必須となります。
それ以外に、病気も持たない健康な若い方にも生じることがありますが、運動することで迷走神経が活発になり、房室ブロックを起こすといった通常の機能であり心配しなくても良いといったケースもあります。
■心房細動や心房粗動と診断されたら
心房から新しく電気を発する場所が生じてしまい、たくさんの電気が重なるため心房が細より速く動く不整脈です。原因は高血圧や甲状腺機能亢進症、心臓病などもありますが、多くは老化現象といえます。
心房細動から脳梗塞を合併しやすいといいますが、予防としてワーファリンを服用していることで安心できます。
心房細動と心房粗動は内服に頼った治療というよりは日常生活において、アルコールの摂取を控える、精神的肉体的ストレスをためないといったことの方が重要となりますので、自己の生活習慣を見なおしてみましょう。
■脚ブロックと診断されたら
脚ブロックには左右によってやや違ってきます。
右脚ブロックでは先天的な心疾患がない限り、ほとんどは病気由来がないもので、治療することが少ないものです。
反対に左脚ブロックは、心疾患が背景にあることが多いので、精査が必要となりますし、運動制限などがある場合がありますので、医師に確認するようにしましょう。
病院で行われる不整脈治療
不整脈の治療は背景にある病気治療が優先ですが、不整脈そのものも対処していかなければなりません。内服薬治療は当然とされてきましたが、非薬物治療として画期的な方法が取り入れられてきています。
■ペースメーカー
正常なリズムを伝える発信機と、そのリズムをつなげる電線であるリードで構成された器械です。リード線は心臓につながる静脈につなぎ、発信機は鎖骨下部分に埋め込みとなります。埋め込みといっても局所麻酔のみで対応となるため、手術時間も1~2時間と短時間で終了します。
ペースメーカーの機種によっても違いますが、5~10年程度で交換が必要となります。
■カテーテルアブレーション
これまでは手術で対応するしかなかった病変を、開胸せずに治療できるようになった方法です。
足の付け根の血管から直径2mm程度の細いカテーテルを挿入し、先端を心臓の異常部分に持って行き、高周波電流で焼くといった処置になります。
局所麻酔で行えるため患者さんの負担も少なく、翌日には歩行も可能となります。
不整脈についてのまとめ
不整脈といっても多くのものがありますが、心臓の病気だから怖いと思い込み、全てに対して腫れものを触るかのような扱いをする必要はありません。不整脈そのものよりも背景となる病気が恐ろしいということが重要なのです。
不整脈の有無を確認すること、どんな不整脈でどんな対処が必要なのかをしっかり把握することが、重症化を防ぎます。
全ての病気や症状のベースは日常生活の質から始まります。生活習慣を見なおしながら、少しでも病気に対するリスクを少なくしていきましょう。